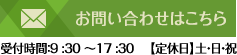-
最新記事
-
アーカイブ
-
カテゴリー
全て

自筆証書遺言の日付について

相続で、亡くなった父親が寄付をしていた場合

年末年始のご案内

訴訟における相手方主張の不当性について

訴訟における主張の長さについて

公益通報者保護法とは

相続と遺産分割⑥

相続と遺産分割⑤