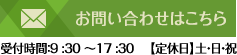-
最新記事
-
アーカイブ
-
カテゴリー
全て

相続と遺産分割②

相続と遺産分割①

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ

義務者が仕事を辞めた場合、養育費は減額されるか

誤送金問題における弁護士費用について

成人年齢引き下げと親権・養育費の終期について

慰謝料は誰がもらえるのか

成人年齢の引き下げについて