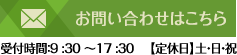訴訟の一般的な流れ
今回は、訴訟の一般的な流れについて書いてみたいと思います。
多くの方は、訴訟について小説やドラマなどからイメージがあったとしても、実際に経験した方は少ないと思います。
まず、訴訟は大きく分けて刑事と民事の2種類があります。
刑事事件は、犯罪行為を疑われた人が国の検察官から起訴され、有罪か無罪か、ふさわしい量刑はどの程度かなどを判断するものです。
民事事件は、払うべきお金を払わなかったり、人に損害を与えたような場合に、私人同士で、お金の支払などを求めて訴えを起こし、請求権があるかどうか、支払うべき金額がいくらかなどを判断するものです。
ドラマなどでは刑事事件が扱われることが多いのですが、一般の方が経験する可能性が高いのは民事事件の方かと思いますので、今回は民事事件について、訴訟の流れを書いてみたいと思います。
まず、相手方と何らかのトラブルがあって、話し合いで解決できないような場合に、支払を求める方が原告となり、相手方を被告として、裁判所へ訴状や証拠の書面を提出することで、手続が始まります。
裁判所で事件が受け付けられた後、被告へ訴状と証拠の書面一式が送られます。
同時に、裁判所での第1回弁論期日も指定され、被告への呼出状が同封されます。
第1回弁論期日において、被告が何も言い分を提出せずに出頭しなかったり、出頭したが請求の原因となる事実を認めた場合、1回で期日が終わり、判決期日が指定され、判決が言い渡されることになります。
ただし、被告が出頭していた場合、判決の代わりに、和解ができないか話し合いが行われることもあります。
第1回弁論期日において、被告が反論を提出し、根拠となる証拠を提出するなどした場合、次回期日が指定され、原告がそれに対する再反論を行います。
それに対し、被告がさらに反論があれば再々反論を行うなど、約1か月ごとに期日が指定され、主張と反論が何度か往復することになります。
原告と被告の主張と反論、及び、お互いの証拠が出揃った段階で、原告被告本人の尋問や証人の尋問を行う期日を指定し、尋問を行います。
事案によっては、尋問の前後で裁判所から和解の提案があり、和解の話し合いをすることもあります。
もし和解が成立すれば、和解調書を作成し、裁判は終了します。
和解が成立しない場合、判決期日が指定され、裁判官が原告被告の全ての主張、証拠、尋問の内容などを精査して、判決を出します。
以上が、一般的な民事訴訟の流れとなります。
※当事務所へのご相談予約・お見積りは、電話または以下のフォームからお問い合わせください。
http://www.ikunami-law.com/contact/