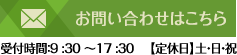訴訟はディベートではない
民事訴訟において、裁判官は原告の主張と被告の主張のどちらが正しいかを判断するのですが、これはどのような基準で判断されるのでしょうか。
法的にどのような事実があったときに、どのような効果が発生するのかは、民法などの実体法に規定されています。
例えば、売買契約の場合、民法555条に、「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
つまり、売買契約は、「一方が何らかの財産を相手方に譲り渡し、相手方がその対価として代金を支払う約束をする契約」となります。
「約することによって、その効力を生ずる」とあるので、約束をした時点で効力が発生します。
したがって、どのような内容で契約したのか、どういった合意があったのかが重要となります。
よく言われる、口約束でも契約というのはその通りです。
しかし、契約したかどうかが争いとなって、相手方が否定しているときに、約束したじゃないかと声を荒げても意味がありません。第三者である裁判官が見ても、契約の合意があったと分かるような証拠が必要です。
そのために、契約書などの書面を作成します。
したがって、裁判で売買契約があったかなかったかが争われた場合、通常は売買契約書を証拠として提出します。
もっとも、売買契約書を提出された相手方が、その売買契約書は偽物であるとか、私が署名したものじゃないといった主張をすることがあります。確かに契約書が偽物だったり、署名が本人のものじゃなければ、契約が成立していない可能性が出てきます。
その場合、相手方の方で、契約書が偽物であることの証拠や、署名が自分のものとは違うことの証拠を提出することになります。
そのように、法律の定めにしたがって、お互いが主張と反論、それぞれの証拠を提出していき、最終的に裁判官がそれらを見て、「法的に」売買契約があったかなかったかの判断をします。
たまに、弁護士が就いていない本人訴訟などでは、そういった事実関係の主張ではなく、相手方の書面の言い回しに揚げ足をとった主張や、相手方の主張が認められるのがいかに不当かと述べる内容を延々と書いた書面が出されることもあります。
しかし、訴訟手続としては、上記のとおり、訴状で請求されている内容(例えば売買代金として金〇〇円支払え)という効果が発生するために、必要な事実があったかどうか、必要な事実を認めるだけの客観的な証拠があるかどうかが最も重要になります。
したがって、いかに文章表現を駆使して相手方をやり込めるような書面を出しても、法的に必要な事実に関する主張が足りなければ認定されませんし、それを認めるだけの証拠が伴っていなければやはり認定することはできません。相手を言い負かしたから認められるというものではありません。タイトルに書いた訴訟はディベートではないというのは、そういう意味です。